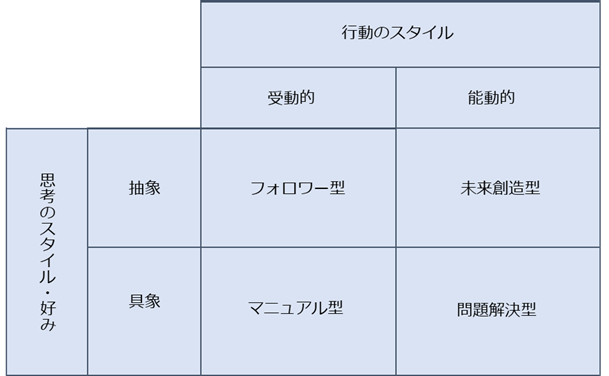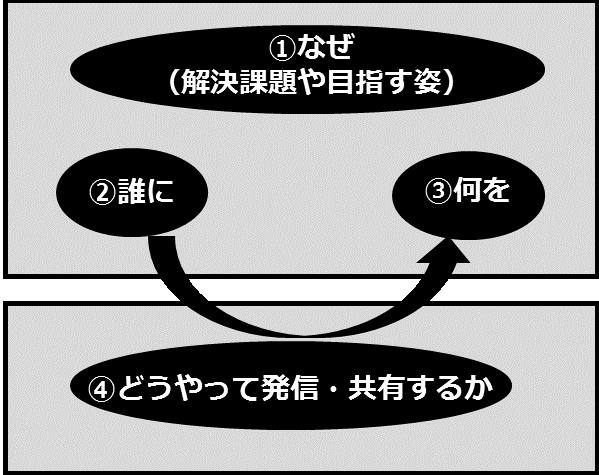2017年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、兼任広報担当者向けに、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。
内容を一部加筆・修正して掲載します。
ホームページ活用のポイント
今号では、ホームページ活用のポイントをご紹介します。ホームページの利活用は、販売促進が中心になることも多いですが、この連載は総務の方が広報業務を兼任する場合を想定しているため、マーケティングサイトではなく、企業情報を発信するサイトについて扱います。
ホームページのトレンドは、大きく以下の3つがあります。
1 ビジュアル化
2 社内広報とのボーダレス化
3 マネジメント能力の訴求
それぞれご紹介しましょう。
ビジュアル化はさらに進む
11月号でお知らせしたとおり、情報の受け手は、情報接触環境が激変し集中力の持続時間が短くなっています。一瞬で多くの情報を伝達するために、ホームページのビジュアル化が進んでいます。たとえば従来、「リンク」はテキスト形式(文字リンク)が中心でしたが、画像形式が多くなっています。動画も多用されるようになりました。
ビジュアル対応が必要になる一方、多くの企業が戸惑うのは「手持ちの写真が圧倒的に少ない」ことです。たとえば、ホームページのリニューアルで「使える写真」が少ないと、著作権フリーの写真素材に頼りがち。ところが、業種・業態にフィットする著作権フリーの写真素材は、競合も似た素材を使用していることも。競合とまったく同じ写真を使ってしまうという失敗例も減りません。
世の中の情報量は今後も増え続けますので、人間の集中力の持続時間はさらに短くなっていくことでしょう。ホームページのビジュアル対応がさらに必要になることは間違いありません。普段からオリジナルの写真をストックしておきましょう。カメラマンに依頼する場合は、必ず利用媒体を無制限にして買い取っておきましょう。多少コストが上がりますが、写真は多いほど用途も発想も拡がります。あらゆる顧客接点で自社理解が進みやすくなる投資と考えれば安いものです。
社内広報とのボーダレス化
近年、社員インタビューや開発秘話などを、継続的に「ストーリーコンテンツ」として発信する企業が増えています。これまで企業のホームページは、ニュースリリースや新着情報を更新するだけで、コンテンツが追加されることはめったにありませんでした。ところが、数年前から採用サイトで「プロジェクトストーリー」を発信するアプローチが流行り、この技法が企業サイト全体に拡がってきています。実は、情報の受け手は、経営者や広報よりも「社員が話すこと」を一番信用するという調査結果もあります。「誰が語るか」によって伝わり方が異なるので、社員をメディアとして活用する企業が多いのです。
ところが、こうしたストーリーコンテンツは、総じて閲覧数が伸びにくくなってきています。「ユーザーが飽きた」「ユーザーはその会社の思いや取り組みに興味を持ち続けるほど暇ではない」というのが現実です。労力やコストのわりに「社外広報」としての効果を実感しにくくなってきています。
こうした取り組みを進める企業からは、別軸の評価がよく聞かれます。社員のモチベーションアップにつながるというものです。会社の顔として登場すれば仕事に対する責任感も増す。ホームページの活用が進んでいる企業ほど、ホームページを「社内を意識した社外広報ツール」ととらえるようになってきています。兼任広報にとっては社外広報と社内広報を一体的にできるので有効でしょう。
マネジメント能力の訴求
昨年(2016年)から今年(2017年)にかけて「ESG情報開示」がブームのようになり、上場企業の多くが「統合報告書」の発行に踏み切りました。統合報告書のコンテンツを生かして、ホームページを見直す企業もあります。ESG情報開示は必ずしも上場している大手企業だけの問題ではなく、近い将来、非上場の会社のホームページでの情報発信にも影響が生じることでしょう。
そもそもESG情報開示とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとったものです。情報開示の対象は投資家です。投資家が中長期的な時間軸で企業の成長性を見極めるためには、その企業が地球規模の視座で環境のリスクと機会をどう認識し対応しているか、人類社会の視座で社会課題のリスクと機会をどう認識し対応しているか、企業の視座で経営陣が企業経営の能力を持っているかを評価できる材料が必要です。中長期の投資判断に資する情報を開示するものが「ESG情報開示」です。
大手企業がESG情報開示を進めるほど、投資家以外もその情報を活用するようになります。たとえばグローバル企業ほど様々な国での法的規制に沿って、サプライチェーン全体で、外注先を含めた環境や社会問題への対応が問われるようになっています。このため、外注先を比較検討する場合、仮に同じような提案内容だったとき、環境・社会問題への対応状況も重要な後押し材料になります。長期投資を呼び込みたい大手企業だけでなく、大手からの請負が多い中小企業にとっても切実な問題になっていくことでしょう。
もちろん、上場企業と同じレベルでESG情報開示が必要という意味ではありません。ESG情報開示では、ESGに関連したデータと「マネジメント能力」が問われます。マネジメント能力とは、経営環境認識とマネジメントサイクル(PDCA)に集約されます。だからこそ、マネジメントサイクルを回していることが理解できる状態にする必要があります。環境対応、従業員の育成や多様性尊重、調達先とのパートナーシップ、お客さまとのコミュニケーション、あるいはコーポレート・ガバナンス等々、過去から現在に至るまで取り組みをどう発展させてきているのか、時間軸を意識して対応の高度化を訴求すると良いです。 ありがたいことに大手企業の統合報告書でたくさんヒントがあります。大手の情報開示を積極的に「マネ」しましょう。